この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、現地取材を元に「車中泊旅行における宿泊場所としての好適性」という観点から作成しています。
※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。
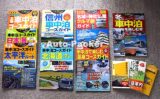
信州の車中泊事情は、「悪化」に向かって進行中。

筆者が知るかぎり、信州の車中泊事情は以前よりも明らかに悪化している。
具体的には、諏訪湖の湖畔にある複数の無料駐車場や、白馬の八方尾根にあるトイレ付きのゲレンデ駐車場が「車中泊禁止」になり、「道の駅風穴の里」や「道の駅白馬」では、かつて24時間使えた可燃物のゴミ箱が店内に移され、営業時間中にしか利用できなくなっている。

そうなった理由をひとことでいえば、「マナー違反」に起因するのだろう。
しかし信州に関わらず、世の大半の車中泊旅行者にすれば、「身に覚えのないこと」で一方的に排除され、不便を強いられるようになったのだから、本来は受け入れ難い話だ。
ほんの「一握りのマナーが守れない人」に、スポットを当てるからそうなるのだが、逆に圧倒的多数の「マナーを守っている車中泊旅行者」の側から見れば、まったく景色は違ってくる。
車中泊のマナー違反はコンビニの「万引き」と同じで、世の中がどう変わろうと、一定数の「悪」は排除できない。
某高校の生徒が、あるコンビニ店で万引きをしたからといって、その高校の制服を着ている生徒全員を「露骨に危険視」したら、そりゃ本人たちだけでなく、学校もPTAも黙ってはいない(笑)。
では、善良なる車中泊の旅人」にとっての、学校とPTAはどこの誰なんだ?
この話は日本中に共通している話なので、また別の記事で続きを書こう。

今の状況下で筆者にできるのは、まずは正確な現状を伝え、その中でもまだ快適に車中泊ができる施設を見つけて、紹介することしかない。
もちろん意識しているのは、圧倒的多数の「善良な車中泊旅行者」だ。
たとえ一部の不埒な輩が同じ情報を見たとしても、「善良な車中泊旅行者」が望む情報を見ることの妨げになることは許されない。
ただ当サイトは、「車中泊ありき」ではなく、「観光やアウトドアなど、車中泊をする本来の目的のために使える車中泊スポット」という観点に立っている。
この点においては、今流行りのVANLIFEさんたちとは明らかに一線を画しているはずだ。
車中泊にライフ(暮らし)を持ち込めば、旅人ではなく「車上生活者」になるのは道理で、場所が道の駅だろうと人様の家の軒先だろうと、スタンスは大いに違ってくる。
筆者の肩書きは「車中泊専門家」ではなく、「クルマ旅専門家」だ。
信州の車中泊事情と車中泊スポット











